第一章:江戸の夜空に咲いた二つの華
二百六十余年続いた徳川の世。大きな戦乱が遠い過去のものとなり、江戸の町が世界有数の大都市として成熟しきっていた頃、庶民のエネルギーは新たな文化を次々と花開かせていました。歌舞伎、浮世絵、相撲…そして、夏の夜を焦がす「花火」もまた、この泰平の世が生んだ最高のエンターテインメントだったのです。
その中心地は、現在の東京・両国。当時、江戸一番の繁華街であり、隅田川にかかる両国橋の周辺は、見物客でごった返していました。1733年(享保18年)、前年に起こった大飢饉(享保の大飢饉)の犠牲者を慰霊し、悪病退散を祈願するため、八代将軍・徳川吉宗が催した「川開き」が、隅田川花火大会の原点とされています。この川開きで打ち上げられた花火が、江戸の庶民の心を鷲掴みにしたのです。
この時代の花火界に、燦然と輝く二つの星がありました。それが「鍵屋(かぎや)」と「玉屋(たまや)」です。
伝統と格式の「鍵屋」
まず、その歴史の幕を開けたのは「鍵屋」でした。初代・弥兵衛(やへえ)が、奈良県五條市から江戸へ出て、日本橋横山町で店を構えたのは1659年(万治2年)のこと。もともとは玩具や人形を扱っていましたが、葦の管に火薬を詰めたおもちゃ花火が評判を呼び、やがて本格的な打ち上げ花火を手がけるようになります。
鍵屋の花火は、その堅実で丁寧な仕事ぶりから高い評価を得ていました。代々、弥兵衛を襲名し、その技術は着実に受け継がれていきます。そして六代目・弥兵衛の時代、ついに鍵屋は幕府御用達の花火師、すなわち「御用火術師(ごようかじゅつし)」の栄誉を手にします。これは、鍵屋の花火が、品質、安全性ともに最高水準にあることを幕府が認めた証であり、その名を江戸中に轟かせる決定的な出来事でした。鍵屋の花火は、いわば「伝統」と「格式」の象徴。派手さよりも、計算され尽くした精巧な美しさ、安定した質の高さで、時の権力者たちからも厚い信頼を得ていたのです。
彗星のごとく現れた「玉屋」
一方、鍵屋の牙城に果敢に挑んだのが「玉屋」です。玉屋の初代・市兵衛(いちべえ)は、もともと七代目鍵屋に仕える腕利きの番頭でした。その才能を高く評価され、1810年(文化7年)に暖簾分けを許され、独立を果たします。鍵屋から分かれたとはいえ、その拠点は師匠である鍵屋と同じ両国橋のたもと。ここから、江戸の夜空を二分する、壮絶なライバル対決の火蓋が切って落とされたのです。
玉屋の花火は、師匠である鍵屋のそれとは対照的でした。もし鍵屋が「静」ならば、玉屋はまさしく「動」。常に新しい技術や演出を追い求め、観客をあっと驚かせるような、華やかで革新的な花火を次々と打ち上げました。例えば、花火が開いた後に、さらに小さな光が時間差で変化していくような複雑な仕掛けは、玉屋が得意とした演出だったと言われています。
その独創性は、江戸の庶民の心を熱狂させました。人々は、伝統的で格調高い鍵屋の花火に感嘆しつつも、次に何が飛び出すか分からない玉屋のサプライズに胸を躍らせたのです。浮世絵師・歌川広重が描いた『東都名所 両国橋下涼舟之図』には、両国橋を挟んで「鍵屋」「玉屋」と書かれた花火船が浮かび、人々がその競演に沸く様子が生き生きと描かれています。まさに、江戸の二大スターの競演でした。
両国橋の上流を「上」の鍵屋、下流を「下」の玉屋が担当し、交互に花火を打ち上げる。観客は、その出来栄えを自分の目で確かめ、優れたと感じた方の屋号を大声で叫ぶ。
「かぎやー!」
「たまやー!」
この声援の大きさこそが、その夜の勝敗を決めるバロメーターでした。それは単なる花火大会ではなく、二人の職人が己のプライドと技術のすべてを賭けてぶつかり合う、真剣勝負の舞台だったのです。そして、その人気は次第に、革新的な玉屋へと傾いていったと言われています。
第二章:「たまやー」「かぎやー」掛け声の謎
花火が最高潮に達した瞬間、夜空に響き渡る「たまやー!」の声。なぜ私たちは、数百年も前の花火師の名前を今も叫び続けるのでしょうか。この不思議な習慣の裏には、江戸っ子の粋な心意気と、日本人ならではの共同体意識が隠されています。
掛け声は「評価」であり「声援」だった
前章で述べた通り、この掛け声の原点は、両国川開きにおける鍵屋と玉屋の競演にあります。観客は、ただ黙って花火を眺めているだけではありませんでした。彼らは、一流の評論家であり、熱狂的なサポーターでもあったのです。
「今の花火は見事だ!さすがは鍵屋!」
「いや、さっきの玉屋の仕掛けには敵わねえ!」
こうした思いを、屋号を叫ぶという形で表現したのが始まりです。それは、現代のスポーツ観戦でひいきのチームや選手の名前を叫んだり、コンサートでアーティストに声援を送ったりする感覚と非常に近いものだったでしょう。自分の声援が、職人たちの次なる創作意欲を掻き立てる。観客もまた、花火大会を構成する重要な一員であるという意識が、そこにはありました。
なぜ「玉屋」と「鍵屋」だけが残ったのか
江戸時代には、もちろん玉屋と鍵屋以外にも多くの花火師が存在しました。しかし、なぜこの二つの屋号だけが、時代を超えて掛け声として生き残ったのでしょうか。
その最大の理由は、やはり「両国川開き」という、当時最大の花火イベントで繰り広げられたライバルストーリーの圧倒的な知名度にあります。鍵屋は幕府御用達のトップブランド。対する玉屋は、そこから独立し、新しいスタイルで人気をさらう風雲児。この分かりやすい対立構造は、庶民にとって最高のエンターテインメントでした。物語性があったからこそ、人々の記憶に強く刻み込まれたのです。
さらに、語感の良さも一因として挙げられます。「たまや」「かぎや」ともに、母音が「あ」の音で終わり、歯切れが良く、大声で叫びやすい。これも、掛け声として定着する上で重要な要素だったと考えられます。
掛け声に込められた江戸っ子の「粋」
この掛け声は、単なる人気投票ではありませんでした。そこには、江戸っ子特有の美意識である「粋(いき)」が深く関わっています。
彼らは、ただ美しい花火を褒めるだけではありませんでした。たとえ少し失敗したように見えても、「よっ、玉屋!次も期待してるぜ!」といった励ましの意味を込めて声をかける。あるいは、素晴らしい花火を見せた職人への称賛と感謝を、最大級の賛辞として屋号を叫ぶことで伝える。そこには、作り手と受け手の温かい心の交流がありました。
また、この掛け声は、花火が上がる「間」を埋める役割も果たしていました。次の花火が打ち上がるまでの静寂の時間に、余韻を楽しむように屋号を叫ぶ。これにより、花火大会全体にリズムと一体感が生まれます。これもまた、場を盛り上げるための洗練された作法、すなわち「粋」な振る舞いだったのです。
民俗学から見る掛け声の役割
民俗学的な視点で見ると、この掛け声は祭りの場で人々が共有する「ハレ」の感覚を高めるための装置であったと解釈できます。花火大会という非日常の空間で、大勢の人が同じ言葉を叫ぶことで、そこにいる人々は一体感を覚え、興奮は増幅されます。個人の感想が、掛け声によって共同体の共有体験へと昇華されるのです。
この「たまやー、かぎやー」という掛け声は、単なる花火師の屋号を超え、日本の花火文化そのものを象徴する文化的アイコンとなりました。それは、職人への敬意、観客同士の連帯感、そして江戸から続く風情を今に伝える、生きた文化遺産と言えるでしょう。
第三章:玉屋、悲劇の終焉
江戸の夜空を席巻し、その人気は本家・鍵屋を凌ぐとまで言われた玉屋。その栄華は、しかし、あまりにも儚く終わりを告げます。彗星のごとく現れ、庶民の心を照らした光は、燃え盛る炎とともに、たった一代で歴史の舞台から姿を消すことになったのです。
運命の夜
1843年(天保14年)4月17日の夜。玉屋の店から火の手が上がりました。乾いた風にあおられた炎は瞬く間に燃え広がり、近隣の武家屋敷や町家を巻き込む大火事へと発展してしまいます。
江戸の町は、木造家屋が密集していたため、一度火事が起きると大惨事につながりやすいという宿命を背負っていました。「火事と喧嘩は江戸の華」という言葉がありますが、これは決して火事を歓迎していたわけではありません。むしろ、それだけ頻繁に起こる、避けては通れない災厄であったことの裏返しです。そのため、幕府による火の元の取り締まりは非常に厳しく、失火に対する罰もまた、極めて過酷なものでした。
玉屋の火事は、幸いにも死者を出すには至りませんでしたが、その被害は甚大でした。この失態に、幕府は厳しい裁きを下します。
江戸所払いという重罪
玉屋の当主であった初代・市兵衛は、この火事の責任を一身に負わされることになりました。その判決は「江戸所払い(えどところばらい)」。これは、江戸の市中から追放され、二度と江戸の地を踏むことを許されないという、当時の庶民にとっては死罪に次ぐ重い刑罰でした。財産は没収され、家も取り潰し。江戸で築き上げたすべてのものを失い、市兵衛はたった一人、故郷とも言える江戸の町を去らなければなりませんでした。
なぜ、これほどまでに厳しい処罰が下されたのか。それは、玉屋がただの町人ではなかったからです。彼は、幕府からもその存在を認められるほどの人気と影響力を持つ花火師でした。その店の失火は、単なる一個人の失敗ではなく、江戸の治安を揺るがす重大事件と見なされたのです。時の幕府は、老中・水野忠邦による「天保の改革」の真っ只中。綱紀粛正と贅沢の禁止をスローガンに、社会の引き締めを図っていた時期でもありました。庶民に人気のあった玉屋の失態は、改革を進める幕府にとって、見せしめとして格好の標的となった側面もあったのかもしれません。
なぜ玉屋は断絶したのか
しかし、一つの疑問が残ります。なぜ当主一人が追放されただけで、「玉屋」という屋号そのものが消滅してしまったのでしょうか。弟子や親族が後を継ぎ、暖簾を再興する道はなかったのでしょうか。
ここには、江戸時代の職人の世界の厳しさと、暖簾が持つ意味の重さが関係しています。当主の追放と家財の没収は、その家が持つ社会的信用と経済的基盤の完全な崩壊を意味しました。特に、火薬という危険物を扱う花火師にとって、幕府からの信頼を失うことは致命的です。失火という最大の禁忌を犯した玉屋の屋号を、誰かが引き継いで商売を再開することは、事実上不可能だったのです。
また、暖簾分けを許した師匠である鍵屋にとっても、弟子の不祥事は大きな打撃でした。鍵屋が玉屋の再興に手を貸すことは、幕府の裁定に逆らうことになりかねず、自らの立場をも危うくする行為でした。こうして、江戸の夜空を彩った革新の光「玉屋」は、誰にも救いの手を差し伸べられることなく、その歴史に幕を閉じたのです。
もし、あの日、あの火事がなければ。玉屋の革新的な技術はさらに発展し、日本の花火の歴史は今とは全く違うものになっていたかもしれません。鍵屋との競演が続いていれば、さらに多様で華麗な花火文化が花開いていた可能性もあります。玉屋の悲劇的な結末は、歴史の「もしも」を想像させ、私たちに一瞬の輝きの裏にある儚さと厳しさを教えてくれます。
第四章:鍵屋、伝統の継承と革新
ライバルであった玉屋が歴史の舞台から姿を消した後、鍵屋は再び江戸の花火界における唯一無二の存在となりました。しかし、その後の道のりは決して平坦なものではありませんでした。幕末の動乱、明治維新による価値観の転換、そして戦争の時代。鍵屋は、幾多の荒波を乗り越え、400年近くにわたってその暖簾を守り続けてきたのです。
時代の荒波を越えて
玉屋の不在は、鍵屋にとって競争相手がいなくなることを意味しましたが、同時に、花火文化そのものの活気が失われる危機でもありました。あの熱狂的な競演を知る江戸の庶民にとって、鍵屋一人の舞台はどこか寂しく映ったかもしれません。
さらに、明治時代に入ると、西洋から安価で発色の良い「洋火(ようか)」が輸入されるようになります。それまで日本の花火の主流であった、木炭や硫黄、硝石を主原料とする「和火(わび)」は、オレンジ色を主体とした、素朴で情緒的な光が特徴でした。一方、塩素酸カリウムや金属化合物を使った洋火は、赤、青、緑といった、それまでにはなかった鮮やかな色彩を表現できます。
この新しい技術の波は、伝統的な和火を過去のものとしてしまう可能性を秘めていました。多くの花火師が派手な洋火へと移行していく中で、鍵屋は和火の伝統を守り続ける道を選びます。もちろん、時代のニーズに合わせて洋火の技術も取り入れましたが、その根底には常に、初代・弥兵衛から受け継いできた和火の精神、すなわち「わびさび」に通じる繊細な美意識がありました。派手さだけを追い求めるのではなく、燃焼の過程や消えゆく際の余韻までを計算し、一つの作品として完成させる。それが鍵屋の哲学でした。
十五代続く宗家の誇り
現在、鍵屋の暖簾は、十五代目の天野安喜子(あまの あきこ)氏によって守られています。江戸時代から続く花火宗家で、女性が当主を務めるのは史上初のこと。彼女は、先代である父の急逝を受け、伝統の重みと未来への責任をその双肩に担うことを決意しました。
現在の「宗家花火鍵屋」は、もちろん隅田川花火大会をはじめとする全国各地の花火大会で活躍していますが、その仕事は単に花火を打ち上げることだけにとどまりません。花火の歴史や文化を後世に伝えるための講演活動、安全な花火の楽しみ方を啓蒙する活動、そして伝統的な和火の技術研究と保存。これらすべてが、宗家としての鍵屋が果たすべき役割だと考えています。
公式ウェブサイトやインタビューで語られる十五代目の言葉からは、伝統を守ることの重圧と、それを乗り越えて新しい時代を切り拓こうとする強い意志が感じられます。「伝統とは、革新の連続である」。この言葉は、まさに鍵屋の歴史そのものを表しています。ただ古いものを墨守するのではなく、その時代、その時代で最高のパフォーマンスを追求し続けたからこそ、400年という長きにわたる歴史を刻むことができたのです。
伝統と最新技術の融合
現代の鍵屋の花火は、この「伝統と革新の融合」を最も象徴するものです。例えば、打ち上げのタイミング。かつては職人の勘と経験だけが頼りでしたが、現在ではコンピュータ制御によって、音楽に合わせて0.01秒単位で花火を打ち上げる「ミュージックスターマイン」のような、複雑で芸術性の高い演出が可能になっています。
しかし、そのコンピュータを操り、プログラムを組むのは人間の感性です。そして、打ち上げられる花火玉そのものは、今もなお、一つひとつが職人の手作業によって丹念に作られています。火薬の配合、星(光の粒となる火薬の塊)の詰め方、玉の締め具合。わずかな違いが、夜空に咲く花の形や色、輝きを大きく左右します。最新のデジタル技術と、江戸時代から受け継がれるアナログな職人技。この二つが完璧に融合して初めて、現代の鍵屋が目指す、観客の心を揺さぶる花火が生まれるのです。
玉屋という永遠のライバルを失った後も、鍵屋は時代の変化という新たなライバルと向き合い、戦い、そして見事に伝統の灯を守り抜きました。その姿は、一瞬の輝きにすべてを賭ける花火そのもののように、力強く、そして美しいのです。
第五章:現代に生きる玉屋と鍵屋の魂
玉屋が姿を消してから、約180年の歳月が流れました。しかし、その魂は、今もなお日本の花火文化の中に生き続けています。そして鍵屋は、その伝統を背負いながら、未来の夜空を見つめています。私たちの心を捉えて離さない花火の魅力、そして「たまやー」という掛け声の先に、二人の花火師の物語はどのように続いているのでしょうか。
花火の科学:和火の再評価
明治以降、一時はカラフルな洋火が全盛となりましたが、近年、その対極にある「和火」の魅力が再評価されています。科学的に見ると、この二つの違いは燃焼の仕組みにあります。
洋火が、金属塩が特定の温度で発する「炎色反応」を利用して、鮮やかな色彩を生み出すのに対し、和火は木炭そのものの燃焼による光が主体です。和火の基本色は、燃える炭の火の色、すなわち赤みがかったオレンジ色(これを「炭火色」と呼びます)です。
一見、地味に思えるかもしれません。しかし、和火には洋火にはない独特の魅力があります。それは、光の「情緒」です。和火の光は、線香花火のように、はかなく、繊細で、温かみがあります。そして最大の特徴は「引き」と呼ばれる、光の尾の長さと美しさにあります。星が燃え尽きながら落ちていく様子は、まるで柳の枝が垂れ下がるかのようにも、筆で線を引いたかのようにも見え、その消えゆく様にこそ美を見出す、日本的な美意識を体現しています。
玉屋も鍵屋も、この和火の技術を極めた職人でした。玉屋の革新性も、この和火の表現の可能性を追求した結果だったのです。現代において和火が再評価されていることは、玉屋と鍵屋が追い求めた美の世界が、時代を超えて普遍的な価値を持っていることの証明と言えるでしょう。
掛け声の今:「たまやー」に込められる想い
では、現代の花火大会で叫ばれる「たまやー」の掛け声には、どのような意味があるのでしょうか。もはや、そこに玉屋の花火はありません。
今日の「たまやー」は、もはや特定の職人への評価や声援という意味合いは薄れています。その代わりに、いくつかの新しい意味合いを帯びるようになりました。
一つは、**「最高の花火への賛辞」**としての役割です。あまりに見事な花火が打ち上がった時、人々は感極まって、知っている限りの最大の賛辞として「たまやー!」と叫びます。それは、かつて江戸庶民が玉屋の花火に送った熱狂を、現代の私たちが追体験しているかのようです。
二つ目は、**「伝統への敬意とノスタルジア」**です。この掛け声を発することで、私たちは江戸時代から続く日本の花火文化の壮大な物語に参加しているような感覚を得ます。悲劇の天才・玉屋の物語を知っている人にとっては、その名を呼ぶこと自体が、彼の功績を偲び、その儚い運命に思いを馳せる行為となります。
そして三つ目は、**「場の一体感を生む合言葉」**としての機能です。誰かが「たまやー!」と叫ぶと、周囲の人々もつられて声を上げたり、笑顔になったりします。それは、その場にいる全員で感動を分かち合うための、魔法の言葉のような役割を果たしているのです。
興味深いことに、今でも花火大会によっては、「鍵屋より玉屋の掛け声の方が多い」という俗説が囁かれることがあります。これは、玉屋の悲劇的なストーリーが人々の心に強く残り、「判官贔屓(ほうがんびいき)」、つまり悲運のヒーローを応援したくなる日本人的な心情が働いているからかもしれません。消えてしまったからこそ、その存在は永遠の輝きを放ち続けているのです。
なぜ私たちは花火に惹かれるのか
最後に、考えてみたいと思います。なぜ、私たちはこれほどまでに花火に心を奪われるのでしょうか。
それは、花火が「一瞬の芸術」だからかもしれません。職人たちが長い時間をかけて作り上げた結晶が、夜空に打ち上げられ、わずか数秒から数十秒という短い時間で燃え尽きて消えていく。その凝縮された時間の中に、誕生、成長、そして消滅という、まるで人生の縮図のようなドラマがあります。その儚さ、切なさが、私たちの心の琴線に触れるのです。
そして、花火は「共有される感動」でもあります。同じ時間に、同じ場所で、同じ空を見上げ、同じ光に感嘆し、同じ音に驚く。家族、友人、恋人、あるいは見ず知らずの隣の人とも、その瞬間、同じ感動を分かち合うことができます。その一体感が、私たちに幸福感と安らぎを与えてくれます。
玉屋と鍵屋の物語は、この花火の感動を、さらに深い次元へと引き上げてくれます。次にあなたが夜空を見上げる時、思い出してみてください。江戸の夜空を舞台に、己のすべてを賭けて民衆を熱狂させた二人の花火師がいたことを。革新的な花火で庶民の心を掴みながらも、悲劇の炎に消えた「玉屋」。そして、幾多の時代の荒波を乗り越え、その伝統の灯を現代にまで伝え続ける「鍵屋」。
あなたの頭上で開く光の花の中に、その二つの魂が今もなお、美しく競い合っているのが見えるかもしれません。そして、誰かが叫ぶ「たまやー!」の声が聞こえたなら、それは時を超えて、伝説の職人たちに届けられる、私たちからの喝采なのです。



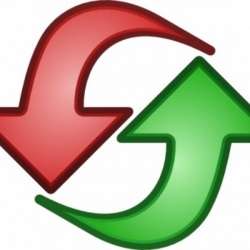 ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:今日のブログ更新
コメント